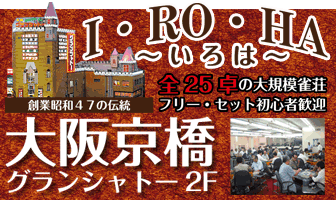牌効率

-
牌効率とはどのような考え方なのか?切る候補のリストアップと比較の繰り返しに極意があります。
-
「枚数が多ければ多いほど有利」なのはという麻雀の基本原則を確認しましょう。
-
牌の持ち方によっては機能が重複してしまうケースがあります。不必要な牌は捨ててしまいましょう。
-
受け入れ枚数と良形への変化という視点で、ターツの機能を比較しています。
-
リャンカンの考え方を中心に、リャンカンのバリエーションを確認します。
-
実戦でも頻繁に見かける複合ターツとその扱いについて。
-
牌効率の練習方法、考え方、うまい人は何が違うのか? 牌理の真髄に触れましょう。
-
配られた段階、あるいは初期の段階ではどのように手を進めていけばよいのか。
-
完成の形がまではっきりと想像できないような搭子が多いケースを見てみましょう。
-
完成に近づく二向聴(リャンシャンテン)時の牌効率を身につけましょう。
-
前回の続き。最も一番機能の低いターツを払うという視点を忘れずに意識してみてください。
-
例外的に発生する七対子(チートイツ)や、雀頭がない場合などの牌姿を確認しましょう。
-
アガリ率に大きく影響を与えるイーシャンテン時の牌理は、手作りでもっとも重要な技術と考えます。
-
イーシャンテン時の牌効率。頻繁に見かける形をパターンとして覚えてしまいましょう。
-
どちらを選択するほうがアガリに近づけるのか? という部分で比較する意識を身につけます。
-
引き続きイーシャンテンの牌理。ノーヘッド形のイーシャンテンに触れています。
-
前回に続き、ノーヘッド形の検証を行います。
-
くっつき形イーシャンテンに触れています。イーシャンテンの牌理は重要なのでページ数が多いです。
-
テンパイ時は選択肢がないケースの方が多いですが具体的なケースを見ていきましょう。
-
効率だけを見るとアガリから遠ざかる「シャンテン戻し」をする場合も中にはあります。