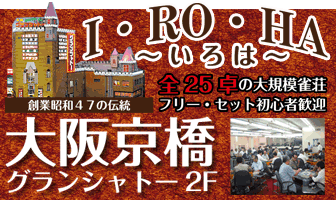リャンシャンテンの牌理(3)
ここまで紹介した2つのパターン当てはまらない手牌について。
1. 4ターツ + 浮き牌
この形は、浮き牌を残すか残さないかが焦点となります。
例1
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() ツモ
ツモ![]()
⇒![]() 切り
切り
例1のように![]()
![]() という明らかに弱いターツがあり、
という明らかに弱いターツがあり、
浮き牌が厚い連続形となっていれば迷わず ![]() を残すところ。
を残すところ。
得点的にタンヤオ・ピンフ・イーペーコーといった手役が狙えるのも魅力です。
例2
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() ツモ
ツモ![]()
⇒![]() 切り
切り
しかし例2は微妙です。![]() 打ちも有力な一手ですが
打ちも有力な一手ですが
大した手役が望めないためストレートに![]() 切りとし、
切りとし、
素直にイーシャンテンへの受け入れ枚数を最大にして良いと思います。
例3
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() ツモ
ツモ![]()
⇒![]() 切り
切り
例3は両面ターツがすでに3組あり、これ以上両面ターツをつくる必要が無いため
![]() を切って確率は低くとも
を切って確率は低くとも
![]() ツモに備えるべきです。
ツモに備えるべきです。
2.ノーヘッド形
ノーヘッド形は難しい選択が多いように思います。
例4
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() ツモ
ツモ![]()
⇒ ![]() 切り
切り
![]() 切りも悪くありませんが、
切りも悪くありませんが、
テンパイスピードは面子優先の![]() 切りが有利。
切りが有利。
イーシャンテンになる枚数は、
![]() を切ると
を切ると ![]()
![]() の6枚減に対し
の6枚減に対し
![]() を切ると
を切ると![]()
![]() の7枚減。
の7枚減。
これだけだとあまり差がないように見えますが、
![]() を切った場合の
を切った場合の
![]() ツモはそれなりに有効牌として機能します
ツモはそれなりに有効牌として機能します
また、![]()
![]()
![]()
![]() の縦引きでマンズ雀頭となった場合にソーズのリャンカンが崩れている
テンパイチャンス4枚減、これはかなり大きいと思います。
の縦引きでマンズ雀頭となった場合にソーズのリャンカンが崩れている
テンパイチャンス4枚減、これはかなり大きいと思います。
変化A
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() ツモ
ツモ![]()
変化B
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() ツモ
ツモ![]()
例5
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() ツモ
ツモ![]()
⇒![]() 切り
切り
![]() と
と![]() の比較ですが、
の比較ですが、
ツモ
![]() はイーシャンテンになるのに対して、
はイーシャンテンになるのに対して、
ツモ ![]() はリャンシャンテン変わらず。
はリャンシャンテン変わらず。
微差ですがマンズの連続形を残した方が有利です。
変化A
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() ツモ
ツモ![]()
変化B
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() ツモ
ツモ![]()
3.七対子含み
七対子リャンシャンテン、すなわち四対子形について。
例6
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() ツモ
ツモ![]()
⇒![]() または
または![]() 切り
切り
面子手ならサンシャンテン、七対子はリャンシャンテン。
なので、トイツに手をかけるわけにはいけません。
一般的にトイツとターツの複合形を残した方が、面子手への移行がスムーズにいきます。
例7
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() ツモ
ツモ![]()
⇒![]() 切り
切り
面子手でも、トイツ手でもリャンシャンテンの手牌は判断に迷うところです。
ピンフが確定するわけでもないので
ここは ![]() 切りで七対子の目をまだ残した方が良いでしょうか。
切りで七対子の目をまだ残した方が良いでしょうか。
例8
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() ツモ
ツモ![]()
これが全て両面ターツなら![]() のトイツ落としピンフ狙いで問題ありません。
のトイツ落としピンフ狙いで問題ありません。