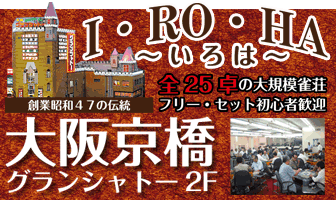リャンシャンテンの牌理(2)
次に一面子完成、4ターツブロックのパターンです。
浮き牌がない場合、選択肢は2つ。
(1)一番機能の低いターツを払う。
(2)ターツブロックを単独ターツにし、4ターツを維持する。
最近の研究では、(1)の打ち方が有力とされているので、
当サイトでも(1)を基本の打ち方とします。
それでは実際の手牌でみていきましょう。
例1
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() ツモ
ツモ![]()
⇒![]() 切り
切り
ソーズのターツが![]() 二度受けなので文句なくここを払うべきです。
二度受けなので文句なくここを払うべきです。
![]() 切りはイーシャンテンへの受け入れを減らす悪手です。
切りはイーシャンテンへの受け入れを減らす悪手です。
例2
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() ツモ
ツモ![]()
⇒![]() 切り
切り
カン ![]() は4枚、
は4枚、![]()
![]() のシャンポンも4枚
のシャンポンも4枚
同じ4枚ならピンフになりやすい打![]() の方が良いのではないか?
の方が良いのではないか?
確かに古い戦術書では ![]() 切りを正解にしているものもあります。
切りを正解にしているものもあります。
しかしイーシャンテンになったときに差が出ます。
変化A
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() ツモ
ツモ![]()
変化B
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() ツモ
ツモ![]()
下の方が良いイーシャンテンなのは明らかです。
![]() はイーシャンテンになっても有効牌として働きます。
はイーシャンテンになっても有効牌として働きます。
![]()
![]() は落とすしかありません。
は落とすしかありません。
また、カンチャンを落とすと手に余裕ができます。安全な牌を1枚持っておくこともできるし、
イーシャンテンへの受け入れがさらに広がります。
変化C
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() ツモ
ツモ![]()
例3
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() ツモ
ツモ![]()
⇒![]() 切り
切り
最も弱いターツを払う、という考え方からするとピンズはシャンポンを含めると8枚の受け入れがあるわけですからここは残します。
マンズとソーズのカンチャンの比較です。
これはソーズの方が両面ターツへ変化しやすく、
マンズは ![]() を引いたとしても二度受けになるのでマンズの払いとなります。
を引いたとしても二度受けになるのでマンズの払いとなります。
例4
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() ツモ
ツモ![]() ⇒
⇒ ![]() 切り
切り
一番弱いターツを払う、という原則を知っていれば、この形でも迷うことはないでしょう。
トイツの比較も、好形変化の種類で行います。
![]() は
は ![]() 引きで三面張になりますし、
引きで三面張になりますし、
![]()
![]()
![]() も有効牌になります。
も有効牌になります。
受け入れ2枚の単独トイツ
![]()
![]() が一番弱い。
が一番弱い。
![]() 切りが正解です。
切りが正解です。
![]() を引いたときの形も、
を引いたときの形も、![]() 切りが一番いいですね。
切りが一番いいですね。
しかし実戦ではターツ比較が困難な場合もあります。
例5
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() ツモ
ツモ![]()
マンズ・ピンズのカンチャンの比較が困難です。
どちらを切っても構わないのですが、
実はシュミレートではカンチャンターツ落としがわずかにテンパイスピードで有利です。
しかし、 この後 ![]()
![]() どちらかが薄くなった場合に
どちらかが薄くなった場合に
状況に合わせた対応できること、
将来 ![]()
![]() 待ちになった場合、
待ちになった場合、![]() の先切り効果で
の先切り効果で ![]()
というメリットがあるため ![]() 切りでも悪くないでしょう。
切りでも悪くないでしょう。
セオリー
「一面子と雀頭完成+四ターツ」のリャンシャンテンは、浮き牌がない場合一番弱いターツを払うのが基本。 ただしターツ判断が困難な場合(明らかに弱いターツがない) 両面固定で判断を先伸ばしにする手もある。