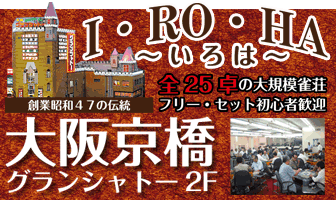面子(メンツ)と搭子(ターツ)
コーツ(刻子)とシュンツ(順子)
麻雀の和了形には四つの面子が必要であり、
面子には(刻子)コーツと(順子)シュンツの2通りがあります。
【順子】![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() … 連続した牌3枚組
… 連続した牌3枚組
【刻子】![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() … 同じ牌3枚組
… 同じ牌3枚組
基本的にコーツよりもシュンツの方がつくりやすい。
麻雀は同じ牌は4枚しかありません。
このうち3枚を集めるのですから、コーツがつくりにくいのは当然です。
しかし鳴きにおいて、
チーは上家からしかできませんがポンはどこからでもすることができます。
鳴く場合はコーツがやや作りやすくなります。
(それでもシュンツより出来やすいということはない)
鳴かずに自力で3枚揃えたコーツを暗刻(アンコー)と言います。 暗刻は作りにくいぶん、三暗刻・四暗刻という役が用意されていますが これらの手役はなかなかできません。
やはり麻雀の面子はシュンツを基本に考えるべきなのです。
まとめ・セオリー
麻雀はコーツとシュンツ、2つの面子がある。
コーツよりシュンツの方が遥かに作りやすいので、
シュンツを基本に手作りするべきである。
ターツとは?
あと1枚ツモればシュンツになるような2枚組を搭子(ターツ)と言い、
ターツには次の3種類あります。
形 |
名前 |
有効牌 | 有効牌の枚数 |
  |
辺張 (ペンチャン) |
 |
4枚 |
  |
嵌張 (カンチャン) |
 |
4枚 |
  |
両面 (リャンメン) |
  |
8枚 |
この表から見て分かるように、リャンメンはペンチャン・カンチャンの倍の受け入れがあり、最も優れた形です。
「リャンメンを作る」、これは手作りの基本中の基本です。
ペンチャンとカンチャンの比較
それでは、一見差がないように見えるペンチャンとカンチャンを比べてみましょう。 リャンメンへの手変わりで差が出ます。
ペンチャン 
 を両面にするためには
を両面にするためには →
→ と引いて来る必要があります。
と引いて来る必要があります。
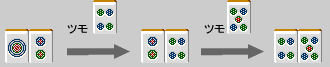
麻雀で2手変わり、というのはかなり絶望的な確率です。
ペンチャンはリャンメンへの変化がほぼ期待できません。
カンチャン
 ならば、
ならば、 を引けばすぐ両面に変わります。
を引けばすぐ両面に変わります。
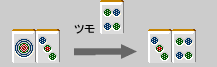
1手変わりであれば、それなりに期待できます。
さらに 
 のようなカンチャンならば、
のようなカンチャンならば、
 のどちらを引いても両面に変化します。リャンメン変化を考えるとペンチャンよりもカンチャンの方が有利ですね。
のどちらを引いても両面に変化します。リャンメン変化を考えるとペンチャンよりもカンチャンの方が有利ですね。
また、手役に関してもペンチャン待ちの場合絶対にタンヤオになりません。 ペンチャンは悪形という認識で良いでしょう。
まとめ・セオリー
ターツには「ペンチャン」「カンチャン」「リャンメン」の3つがあり、
リャンメン >> カンチャン > ペンチャン
と価値に差がある。
リャンメンをつくることは麻雀の基本中の基本である。