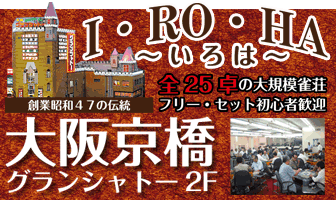テンパイ(聴牌)とシャンテン(向聴)
麻雀の手作りで大切な概念を学びます。
手役よりもまず、手牌を形で捉えることが肝心です。
麻雀のアガリ形
麻雀は言うまでもなく和了形を完成させることを目指すゲームです。
この和了形は大きく分けると3パターンです。
(1)四面子と一対子を完成させる
(2)七対子を完成させる
(3)国士無双を完成させる
(2)と(3)は特殊な和了形で、基本は(1)の四面子形です。
面子には刻子(コーツ)と順子(シュンツ)の2通りがあります。
【順子】![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() … 連続した牌3枚組
… 連続した牌3枚組
【刻子】![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() … 同じ牌3枚組
… 同じ牌3枚組
したがって、牌構成で考えた麻雀の和了形は以下の通りです。
1.四面子一雀頭
1-a 四順子![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1-b 三順子一刻子![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1-c 二順子二刻子![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1-d 一順子三刻子![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1-e 四刻子![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
2.七対子(チートイツ)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()




![]()
![]()
![]()
![]()
3.国士無双(コクシムソウ)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()


![]()
![]()
これらの和了形には作りやすさに差があります。 もちろん一番難しいのは国士無双で、 その見返りとして役満という最高の点数が与えられています。
なお、厳密には面子には同じ牌4枚組の槓子(カンツ)がありますが ここでは刻子との区別をしていません。
テンパイ(聴牌)とは
あと1枚で和了形が完成する形をテンパイといいます。
役があればアガることができます。
【例1】












 か
か でアガれる形です。
でアガれる形です。
麻雀はテンパイしなければ点数をもらえることはありません。(例外は他人のチョンボのみ) また、メンゼン(1枚も鳴いてない状態)であればリーチをかけることができます。 したがって、できるだけ早くテンパイまで持っていくことが重要です。
シャンテン数(向聴数)
【例2】












テンパイまであと一手の状態です。

 を引けばテンパイになります。
を引けばテンパイになります。
このようにあと1枚有効牌を引けばテンパイになる状態を
「一向聴(イーシャンテン)」
テンパイになる受け入れ(この場合は

 )を
)を
「テンパイチャンス」と言います。
テンパイチャンス(の枚数)が多ければ多いほどテンパイしやすく、 優秀なイーシャンテンと考えることができます。
【例3】![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
例3はかなり受け入れ枚数が多く、13種42枚のイーシャンテンです。
例2が3種12枚ですから、4倍近い差があります。
このように、ひとくちにイーシャンテンといっても 牌の組み合わせでテンパイのしやすさには大きな違いが出ます。
テンパイまで最短でも何手かかるか、その最小回数を「シャンテン数」と言います。
シャンテン数が1の手牌を「一向聴(イーシャンテン)」
シャンテン数が2の手牌を「二向聴(リャンシャンテン)」と呼び
以下サンシャンテン、スーシャンテンと続きます。
これは豆知識ですが、麻雀で最もテンパイまで遠いのは六向聴です。
【例4】![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

例4が六向聴の例で、最短の七対子テンパイでも六手かかります。
シャンテン数はアガリまでどれくらいかかるかの目安となる数値であり、大変重要な考え方です。 自分の手が今何シャンテンなのか、感覚的に分かるようになりましょう。少なくとも、イーシャンテンとリャンシャンテンは明確に区別して打つべきです。
シャンテン数を下げる
自分の手がリャンシャンテンならイーシャンテンを、イーシャンテンならテンパイを、テンパイならあがりを目指す、そういう心構えで打つことが大切です。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() ツモ
ツモ![]()
たとえばこの手で、「はじっこだから」「浮いているから」という理由で![]() を切ると手はリャンシャンテンのままです。
を切ると手はリャンシャンテンのままです。
イーシャンテンに進めるため、![]() か
か![]() を切りましょう。
を切りましょう。
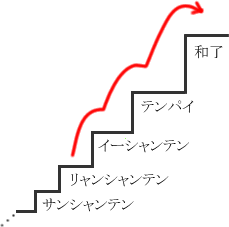
麻雀は図のようなステップをふんで和了までもっていくゲームです。 決して途中で1段飛ばすことはできません。 手によってはシャンテン数を下げない方がよいときもありますが、 基本はシャンテン数を下げるように打牌を考えるべきです。