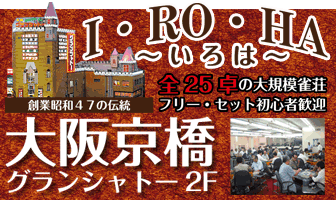麻雀と確率
麻雀の手作りというと、 「どんな手役をつくるか」だと思っている人がいるかもしれませんが、 それは麻雀の本質から外れていると思います。
手作りの本質は「四面子・一雀頭」という形をつくることです。
麻雀を一局単位で捉えるならば、
4人のうち誰が一番早く四面子一雀頭を完成させるかを競うゲームです。
もちろん最終的には持ち点で評価されますが、 ドラ(赤牌を含む)が多く、手役がなくとも高得点が出る現在の麻雀のゲーム性を考えれば やはり本質は「役」ではなく「形」です。
そして一番早く形を完成させた者だけに得点が加算される以上、 必然的にスピードが要求されます。
では、どうすれば早くアガることができるのでしょうか。 そのための考え方が牌効率であり、確率です。
例題1 何を切ればよいか?
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() ポン
ポン![]()
![]()
![]() ツモ
ツモ![]()
最も単純な例で考えてみましょう。
例1は三面子と雀頭が完成したので、あと一面子ができればOKです。
![]() を切ると
を切ると![]() と
と![]() が来れば(出れば)アガリ
が来れば(出れば)アガリ
![]() を切ると
を切ると![]() が来れば(出れば)アガリです。
が来れば(出れば)アガリです。
どちらを切ればアガリやすいかは明白ですね。
例題2 何を切ればよいか?
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() ポン
ポン![]()
![]()
![]() ツモ
ツモ![]()
テンパイ(あと1枚でアガリになる状態)にとれる打牌は![]() と
と![]() です。
です。
![]() を切ると、
を切ると、![]()
![]() 待ち
待ち
![]() を切ると、
を切ると、 ![]()  ̄
 ̄ ![]() 待ちになります。
待ちになります。
どちらも2種類なので、アガリやすさも同じかというとそうではありません。
![]()
![]() は自分でそれぞれ2枚ずつ使っているので残りは4枚、
は自分でそれぞれ2枚ずつ使っているので残りは4枚、
![]()
![]() は8枚全て(自分の手からだけ判断すれば)残っています。
は8枚全て(自分の手からだけ判断すれば)残っています。
クジ引きをするならアタリクジの多い方が得ですよね。
当然枚数の多い![]()  ̄
 ̄ ![]() 待ちに取ったほうがアガリの確率は高くなります。
待ちに取ったほうがアガリの確率は高くなります。
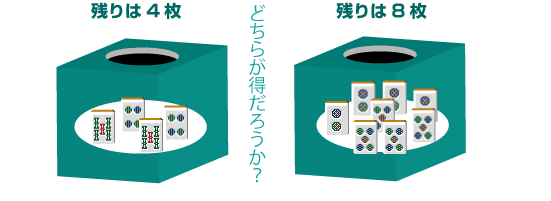
「有利な確率で抽選を受けれるように切る牌を選ぶ」
これが手作りの基本となる考え方です。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() ポン
ポン![]()
![]()
![]() ツモ
ツモ![]()
たとえばここで![]() を切っても、
を切っても、
![]() や
や![]() の方が出てアガリを逃がすことはあります。
の方が出てアガリを逃がすことはあります。
しかしだからといって 「![]() を切っておけば良かった」と考えないようにしましょう。
悪い手を打っても、よく結果オーライになるのが麻雀です。
を切っておけば良かった」と考えないようにしましょう。
悪い手を打っても、よく結果オーライになるのが麻雀です。
結果論の失敗をイチイチ気にすることはありません。
まとめ・セオリー
麻雀は最善手を打ってもしばしば失敗するゲーム。
一時的な結果で一喜一憂するのではなく、
長い目で見てどちらが得なのかを判断する。