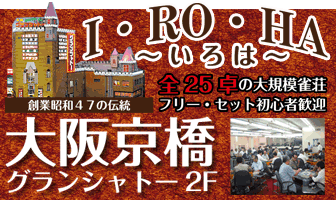鳴きのテクニック(1)
実戦で役立つテクニックを3回に分けて紹介していきます。
こういう小技は知っている人ならば何気なく使っているものですが、
慣れないうちは「鳴く」という発想が出なかったり、
あるいは鳴くことに抵抗を感じたりするものです。
覚えておいて損はありません。
必ず役に立つ場面に出会うはずです。
特に赤入り麻雀では大きな武器になるでしょう。
食いのばし
チーによってメンツを増やすテクニックです。
ホンイツでよく使います。
例1
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
たとえばこの手。
上家が出した ![]() を鳴くのが、食いのばしにあたります。
を鳴くのが、食いのばしにあたります。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
マンズの下で二面子つくることに成功しました。
このような鳴きは、タンヤオでも有効です。
例2
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() ドラ
ドラ![]()
メンゼンでハネ満も狙える手ですが、上家がソーズを切れば食いのばしで
タンヤオドラ3を狙うのが実戦的です。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() チー
チー![]()
![]()
![]() ドラ
ドラ![]()
自力で ![]()
![]()
![]()
![]()
![]() を引きにいくよりも、
を引きにいくよりも、
チーテンが取れる ![]()
![]()
![]()
![]() のイーシャンテン方が
のイーシャンテン方が
単純計算で倍のスピードでテンパイできます。
せっかくのチャンス手も、あがれなければ意味がありません。
例2のように満貫手であれば、いつでもチーする心の準備をしておきましょう。
ダブル面子処理
連トイツをチーして二面子つくるテクニックです。
例3
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
役牌暗刻だとなぜか「もったいない」という意識が働き
メンゼンで仕上げたくなるのが人情です。
例3でも三暗刻やマンズのイーペーを狙ってメンゼンでいく人が多いかと思います。
![]()
![]() くらいはスルーしていいでしょう。しかしポイント牌は鳴くべきだと思います。
くらいはスルーしていいでしょう。しかしポイント牌は鳴くべきだと思います。
この手のキー牌は ![]() と
と ![]()  ̄
 ̄ ![]() です。上家から出たら鳴きましょう。
です。上家から出たら鳴きましょう。
牌理で一度説明していますが、
基本的に![]()
![]()
![]()
![]() や
や ![]()
![]()
![]()
![]() といった二度受けは愚形です。
といった二度受けは愚形です。
この愚形を、鳴きによって解消しようというわけです。
鳴くと非常に軽い形になるのが分かるでしょう。(変化1、変化2)
変化1![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
変化2![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
単純にチーテンに取れるイーシャンテンになっただけではありません。
変化1の場合。もし上家が ![]()  ̄
 ̄ ![]() を再び引いてきたとき、切ってくれる公算が高い。
を再び引いてきたとき、切ってくれる公算が高い。
変化2も同様で、 ![]()  ̄
 ̄ ![]() は非常に鳴きやすくなっています。
は非常に鳴きやすくなっています。
そのような理由で、二度受けが鳴いて解消できるときは、できるだけ鳴くのが望ましいといえます。
ただし、理牌には注意しましょう。
例4
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() ドラ
ドラ![]()
この手で上家から![]() が出たので、A君は喜んでチーします。
が出たので、A君は喜んでチーします。
ところが ![]()
![]() は全く場に出てこず結局流局 --- なぜでしょうか?
は全く場に出てこず結局流局 --- なぜでしょうか?
他家からこの鳴きはどのように見えるかというと、
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
↓「チー!」
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
↓
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() ←注目
←注目
↓
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() ← (´д`)
← (´д`)
↓
こんな形で手牌がばらけてしまうと、ピンズの下が残っているのがバレバレです。
「 ![]()
![]() がド本命、あとは
がド本命、あとは![]() かペン
かペン![]() ぐらいしかないな」と、
ぐらいしかないな」と、
上級者にはガラスのテンパイなわけです。
A君は ![]()
![]() を鳴く前に、理牌を少し変えておく工夫をするべきだったのです。
を鳴く前に、理牌を少し変えておく工夫をするべきだったのです。
例![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
今回紹介した食いのばしや二度受けからの鳴きは、 手牌が不自然な形で残ってしまうことがあります。 慣れてきたら、鳴くことを想定して理牌をするかチー」と発生する前に素早く場に晒す2枚を右に寄せるなどの工夫をしてみましょう。