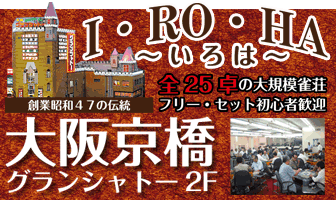鳴きのテクニック(2)
食いタンにおける高度な技術を紹介します。
小手先のテクニックだと言われるかもしれませんが、
現在の赤入り麻雀で差がつくのはこんな小手先のテクかもしれません。
昔手役の花形であった三色はすっかり脇役になってしまいました。
赤牌の導入で台頭して来たのがタンヤオ。
食いタンはスピードにおいて他の手役を圧倒し、
赤を絡めて高さも備えた最強の手役です。
図1 東1局東家6巡目の手牌
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() ドラ
ドラ![]()
こんな手でも、食いタンを考えます。
リーチ狙いだと受け入れはせまく、マン・ピンの両面手代わりを待つことになり遅れを取ります。
上家から ![]()
![]()
![]()
![]()
![]() が出ればチーです。
が出ればチーです。
ピンズ・ソーズでそれぞれ2面子構成で、あとは一直線。
有効牌の枚数は変わらなくても、上家の捨て牌を利用できる分、
スピードはメンゼンより遥かに上で、赤をもう1枚引き込めば簡単に満貫ができます。
(変化した形・・・図2)
図2![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() チー
チー![]()
![]()
![]() チー
チー![]()
![]()
![]()
図1から234や456の三色をイメージするような想像力は要りません。
最高形なんてくだらない概念だと思いませんか?
絵に描いた餅のタンヤオ三色よりも、
現実的な食いタンをイメージすることが大切です
図3 東1局北家5巡目の手牌
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() ツモ
ツモ![]() ドラ
ドラ![]()
ドラ3だからと言って即リーチはどうか?(ヤミテンは超論外)
アガリやすさでも高さでも ![]() 切りが優位に見えます。
切りが優位に見えます。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() を 鳴いて好形テンパイが組めます。
を 鳴いて好形テンパイが組めます。
(ドラポンはレアですが、もし出たらすぐ反応!)
メンゼンならこれに ![]()
![]()
![]() が加わり、
が加わり、
テンパイを崩しても十分お釣りが来ますね。
図4 東1局西家9巡目の手牌
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() ドラ
ドラ![]()
上家が ![]() を切ってきたとします。
を切ってきたとします。
「あ~もう2枚も見えちゃった」と思いながら見過ごしてツモ山に手を伸ばす。
・・・これは緩手です。![]()
![]() のカンチャンで鳴いてタンヤオにするべきです。
のカンチャンで鳴いてタンヤオにするべきです。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
メンゼンでテンパってもドラ表示牌待ちになるのは目にみえています。
ドラそばの ![]() はリーチをかけてもまず出てこないし、
はリーチをかけてもまず出てこないし、
ツモろうにも分かっているだけで残り2枚で期待薄。
アガリ困難なメンゼンに固執する必要はありませんね。
図5東1局東家8巡目の手牌
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() ドラ
ドラ![]()
まさかと思うかもしれませんが、この手でさえ食いタンを考えます。
俺なら![]() が出たら食い換えし(食い換え禁止なら
が出たら食い換えし(食い換え禁止なら ![]() 切り)
切り)
![]() が出たら鳴いて
が出たら鳴いて ![]() を切ります。
を切ります。
メンゼンで進めても苦労しそうな手です。
この巡でこの形では、リーチをかけてアガリきるのは相当難しいでしょう。
ポン、チーできるタンヤオに活路を求めるべきだと思います。
ドラや赤があってあがりたいときや
親でどうしても連荘したいときに食いタンは有効な手段です。
鳴き麻雀を嫌う人はいまだに多いのですが、
下品だと言われようが、そんな時代遅れの苦言はは無視すればいいのです。
この手を鳴ける人が強い、俺はそう思います。